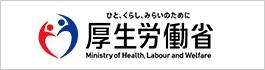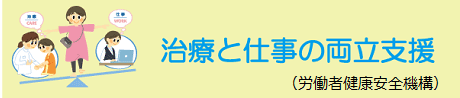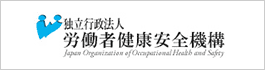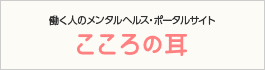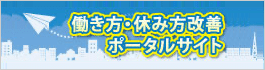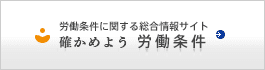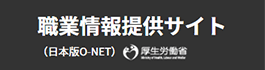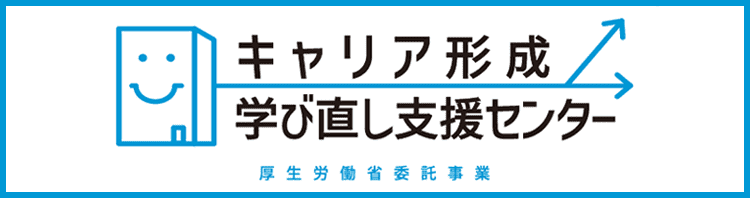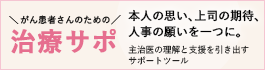両立支援の取組事例
本人の意志を尊重し、心を配ることを大切に
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 津工場

健康管理室 島田 様
- 会社名
- パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 津工場
- 所在地
- 三重県津市藤方1668
- 事業内容
- 電気機械器具の製造、開発
- 設立
- 1943年7月
- 従業員数
- 約1,500名 (工場内のグループ会社含む) (2025年3月現在)
- 平均年齢
- 44.2歳 /男女比 男性6:女性4
- 産業保健スタッフ
- 4名
壁に設置されるコンセントや天井照明をつけるスイッチなどの電気設備を製造する、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社の津工場。電気設備だけでなく、照明空調制御をはじめとした省エネマネジメントシステムや、住宅やビルの電気・情報にかかわるインフラ設備をトータルに提供しています。同工場では、産業医を中心とした産業保健スタッフが、病気を抱える従業員の意志を尊重し、各種部署と連携しながら、治療と仕事の両立支援に取り組んでいます。
当工場では、産業医1名、産業看護職3名の計4名によって、従業員の健康の保持・増進を図っており、その一環として治療と仕事の両立支援に取り組んでいます。がんや糖尿病、神経難病、またはメンタル不調などを抱える従業員への支援は、本人からの相談や、その上司からの連絡を産業保健スタッフが受けて、病気や体調の状態把握を行うことから始めます。その際に重視しているのは、本人の意志です。「治療を続けながら今まで通り働きたい」、「仕事を休んで治療に専念したい」など、本人の意志を尊重しながら、主治医の見解や、職場で可能な配慮、人事部の意見などを踏まえて両立支援を進めています。
具体的な事例として、てんかん(脳の神経細胞が過剰に活動することで、繰り返し発作が起こる病気)のある従業員への支援があります。てんかんの場合、疲労の蓄積によって発作が起きやすくなるケースがあるため、作業強度や就業時間などを考慮する必要がありました。また、強い光や大きな音によっても発作が起きることがあるため、職場環境の見直しも考慮すべきポイントでした。
作業強度や職場環境などについては、主治医の見解も重要になります。当工場の場合、オートメーションのライン作業だけでなく、昔ながらの手組による製造、または試作品開発などの業務もあり、主治医が複雑な作業工程を把握するのは難しい面もあるため、現場を知る産業医が間に入り、主治医と連携しました。産業医から主治医に意見照会を行い、「業務内容は問題ないか」、「車通勤をしても大丈夫か」、「就業中の配慮事項はその他にないか」などの見解を求めながら、本人とも話し合いをしつつ、この従業員への両立支援の方針を定めていきました。
職場の配慮として、安全の確保も重要です。前出のてんかんの従業員の場合、適切な治療によって発作は起こりにくくなりますが、万が一、てんかん発作が起きた場合は、転倒などによってケガをしないよう周りの従業員の協力が必要になります。そのため、てんかんという病気の症状や、発作時の対処法などをまとめた資料を作成して配布するなど、病気の概要を周囲の方々へ理解いただくようお願いをしました。
一方で、病名を知られたくないという従業員もいます。その場合は本人の意志を尊重し、具体的な病名を伏せつつ、「病気があるので」と周りに理解を求めますが、産業医としてはいざという時のために、直属の上司や一緒に作業をする仲間だけには病名をお伝えし、理解いただいた方が良いのでは、と本人にアドバイスしています。
治療と仕事の両立支援をはじめ、工場の従業員に対して健康づくりに関しての情報発信を行っています。近年増えているメンタル不調などは、その兆候などを明記したポスターを掲出して、自身の不調に気づいてもらうことや、何かあればすぐに相談につなげる環境づくりを心掛けています。
治療と仕事の両立支援では、本人の意志に極力沿えるよう、また職場の理解をできるだけ得られるように産業医や産業保健スタッフが間に入り、主治医の見解や、人事部との話し合いを踏まえて、現実的な“落としどころ”を模索していきます。そこで最も大切にしているのは本人の意向で、「どう働きたいか」「どのような状況が本人にとって苦しいのか」など、出来るだけ多くの意見を聞くようにしています。
従業員が安心・安全に長く働き続けられる職場であることは、今後の人材確保にもつながり、長期的に見れば企業にとっても非常に重要なことであると考え、両立支援に取り組んでいます。
取組事例一覧